The 2nd East Asia Migrant & Coexistence Film Festival
1.映画の始まり
2001年の冬だった。恋ひとつしたことない中年未婚男性がウズベキスタンへお見合い旅行に行き紆余曲折を経た後、愛を探して帰ってくるという話のドキュメンタリーを見たのが始まりだった。その時私も結婚をしておらず、最近韓国で国際結婚が話題になっていた。個人的にも社会的にも興味を持った。それで、ドキュメンタリーの主人公に会いインタビューもしてみた。彼はとても純粋で世の中の垢がついていない最近の社会ではなかなか見かけることのできない人であった。どうかすると恋にも憎らしいくらい計算的な現代社会の中で彼は、非常に新鮮で独特なキャラクターとして私の脳裏に刻まれた。彼との出会いから既に私の中では一編の映画が描かれた。日本の<101回目のプロポーズ>と<蒲田行進曲>のような純粋な男性が本当の愛を得るそんな映画である。
2.ウズベキスタンで見た実態
私は実際に結婚をするために遠征に立つ中年未婚男性4人と共に取材を兼ねてウズベキスタンに向かった。飛行機の中で4人の中年未婚男性たちは美しくやさしい女性との未来を設計し、高鳴る心で浮かれており、私もやはり皆がそうでなくても1、2組のカップルでも映画のような楽しい日々が繰り広げられるだろうという思いに興奮した。
しかし私がそこで直面した現実は私たちの希望とははるか遠いものであった。結婚仲介業者の紹介で会った女性は新しい愛の可能性を探しに来たというには瞳に希望の輝きが見られなかった。お見合いに来た女性の瞳に映った未来に対する希望と漠然とした不安とときめきのようなものがひとつになるそのような表情を見ることができなかった。ただ苦しい家庭状況や今の自分の立場より裕福なところで暮らしたい欲望で男性を探していた。韓国から行った男性も実際さほど変わりなかった。はじめは‘何も関係ない、私だけを好きでいてくれる女性ならそれだけで十分だ’と言っていた彼らも時間が許す限りは無制限に女性を紹介してもらえるシステムの中で時間が過ぎるたびにもっといい女性、もっときれいな女性、より若い女性を探し始めた。お金のために昨日までは見ず知らずであった男性と結婚しようとする女性と、女性たちを店の商品を選ぶかのようにさぐる男性たち…まるで人を売買する人間市場のようであった。
3.韓国帰国後の残像
希望にあふれ楽しい話の内容を探しに行き、あまりにも悲惨な現実を見ることになった。韓国に帰国後、シナリオは一行も書けなかった。浪漫ではない生のイメージ。生々しい現実を見てしまったからである。どのように映画を撮らなければならないか検討がつかなかった。現実のリアリティーは映画的リアリティーになりえなかった。
その上、ウズベキスタンに滞在しながら見ることになった2つのイメージは私をより不便にさせた。その中のひとつは高麗人のおばあさんの瞳だった。道でキムチと米を売っていたおばあさんであった。彼女と目が合ったとき、私を見ていた彼女の悲しみと悔恨、恨みそしておぼろげさが入れ混じった一言では言い表せない妙な目つき、そしてTVニュースで報道された中国駐在ドイツ大使館へ侵入しようとする脱北者の凄絶な映像がそれであった。
いずれにしてもこれらを克服するだけでも6ヶ月がかかった。
4.映画に込めたかった思い
韓国に帰って高麗人に対して調査をしてみた。これまで話だけで聞いていたカレイスキー(旧ソ連に住む高麗人)や高麗人、李氏朝鮮時代末から植民地時代に、本格的に移住を始めた彼らにつけられた名前だ。歴史は彼らに貧困と疎外と根気強い生命力を伝えた。
ちょうどその時、ウズベキスタン遠征隊のひとりから連絡が来た。結婚するというものだった。すなわち、ウズベキスタンで出会った女性との結婚であった。彼こそ、私の映画「ウェディングキャンペーン」のユ・ジュンサンのモデルだ。人間市場のような雰囲気の中で、いい女性に出会いはしたが、もっといい女性はいないかという欲望に満ち溢れ、女性を訪ねては膝まずいて頭を下げていたのだった。しかし、最終的に男は何が重要なのかに気がつくのだった。詳しい事情が気になる方は映画をご覧になりたい。
それで私は、まだ希望はあると考えるようになった。いくら、人間を物として取り扱い、お金で人間を判断するような物質主義社会といえども、まだ愛が残っており、それがとても大切なものであることを遅ればせながら、気付いた人がいるのだ。私はやっとシナリオを書き始めた。ララを通して脱北者と高麗人の現実も一緒に扱うことにした。それで私は韓国にいるソ・トミン(韓国に定着した脱北者)のインタビューを始めた。それからウラジオストックに行き、北朝鮮の労働者に会って、彼らの生き生きとした暮らしの現状を確認し、高麗人が第一歩を踏み出したという沿海州にも行った。ウズベキスタンで、さらに多くの取材が始まった。そして映画が完成した。脱北者はララの姿で、高麗人は空港で娘を嫁がせる父親の「金持ちでなくてもいいから、韓国人と同じように接してくれ」という願いとして、描かれることになったのだ。
5.現実に戻り
今日扱っている高麗人、脱北者、結婚移住問題について韓国社会の態度を一言で表現すると‘矛盾的’である。韓国では独特な思想がひとつある。これはまさに‘純潔主義’である、一言で韓国人だけを‘私たち’とするということである。そしてフィリピンやベトナム、ウズベキスタンから来た新婦も高麗人も脱北者も中国同胞も全て‘外部の人’になる。しかし疑問である。‘韓国人’というものが果たしてなんだろうか?韓国国籍を持っている人?(それならばコリアン−アメリカンであるゴルファーのミッシェル・ウィーやアメリカンフットボールのハインズ・ワードに対する韓国人のプライドは何だろうか?)では、韓国に暮らし、韓国人と家族である人?(では、結婚移住女性に対する排他的な態度は何だろうか)、もしくは言葉どおり両親から韓国人の血を譲り受けた人?(では高麗人、脱北者、中国同胞に対する差別は何だろうか?)
韓国人が彼らに抱く態度は何の定立された価値観もない。ただ貧しい人とは友達になりたくなく裕福な人とは友達になりたいという非常に稚拙な欲望以外にはその何ものでもない。
その上、必要であるため外国人女性を新婦として迎えながらも彼らを韓国社会の一員として認めようとしない態度にはもどかしささえ感じる。
今日、私の話しがあまりにも現実の暗い部分だけを照らしているようで心配である。韓国には勿論このような問題について正しい考えを持っているひとも多い。一度は外国人労働者のハングル学校の校長職を受け持っていた青年に会ったことがある。彼は“TVで外国人労働者の現実を取り扱う時、差別を受けて疎外されているかわいそうな姿だけを込めて感情的に同情させるのがあまりにも嫌である。私が知っている限りでは人間身あふれる社長たちがずっと多い。”と言っており、マスコミの扇情性を批判したことがある。正しいことである。しかし私が指摘した暗い面があることも事実である。
韓国社会には正義と不義が混在されており、正当さは賞賛しそのまま置いておけばよい。ただ、私は不義の側面があるならばそれを変えようと努力をしなければならないということを強調したい。50%の不幸な事例で残りの幸せまで色眼鏡をかけてみる必要はない。しかし50%の幸せで残りの不幸に目を背けてはだめだ。
多文化家庭、多様性の受容は、いまや私たちが頭ではなく心で共感しなければならない部分である。映画の中でユ・ジュンサンカップルが現実で子供を生み相変わらず幸せそうに暮らしている姿を通じて私は希望を抱いた。全ての疎外と差別と分かち合いを壊せるのは歴史と社会の現実に対する正しい認識である。歴史と現実をありのまま捉え受け入れなければならない。そしてより重要なことは人間が創りあげた(人種・国籍等)人為的基準ではなく人間そのものであるということだ。
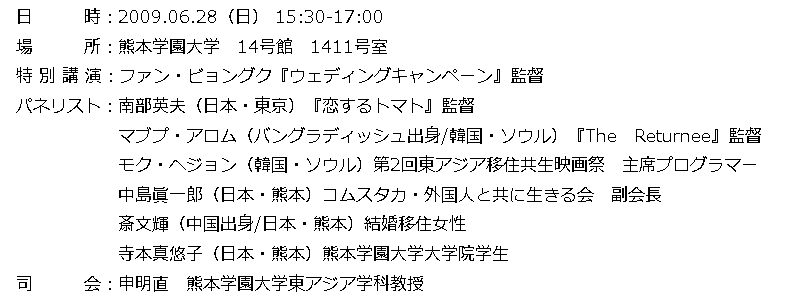
南部監督
モク プログラマー(左)
中島副会長
斎さん
寺本さん